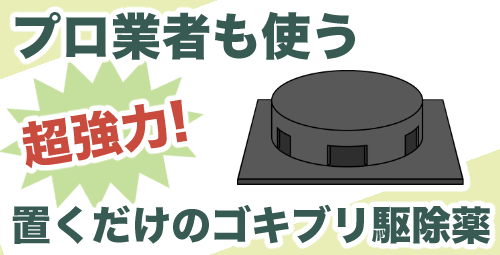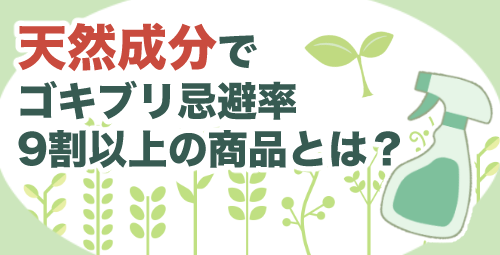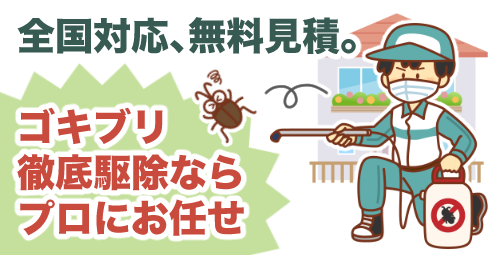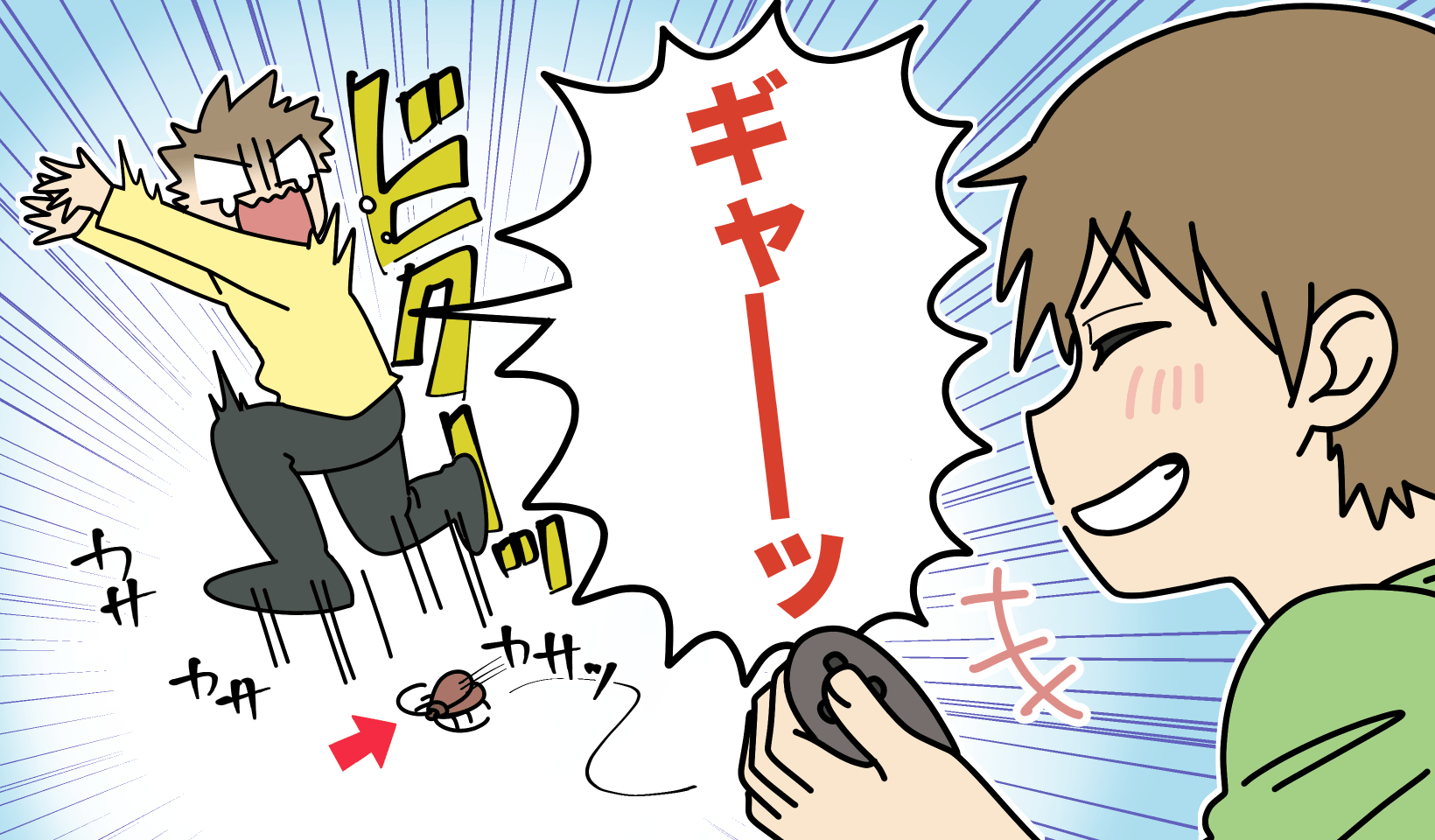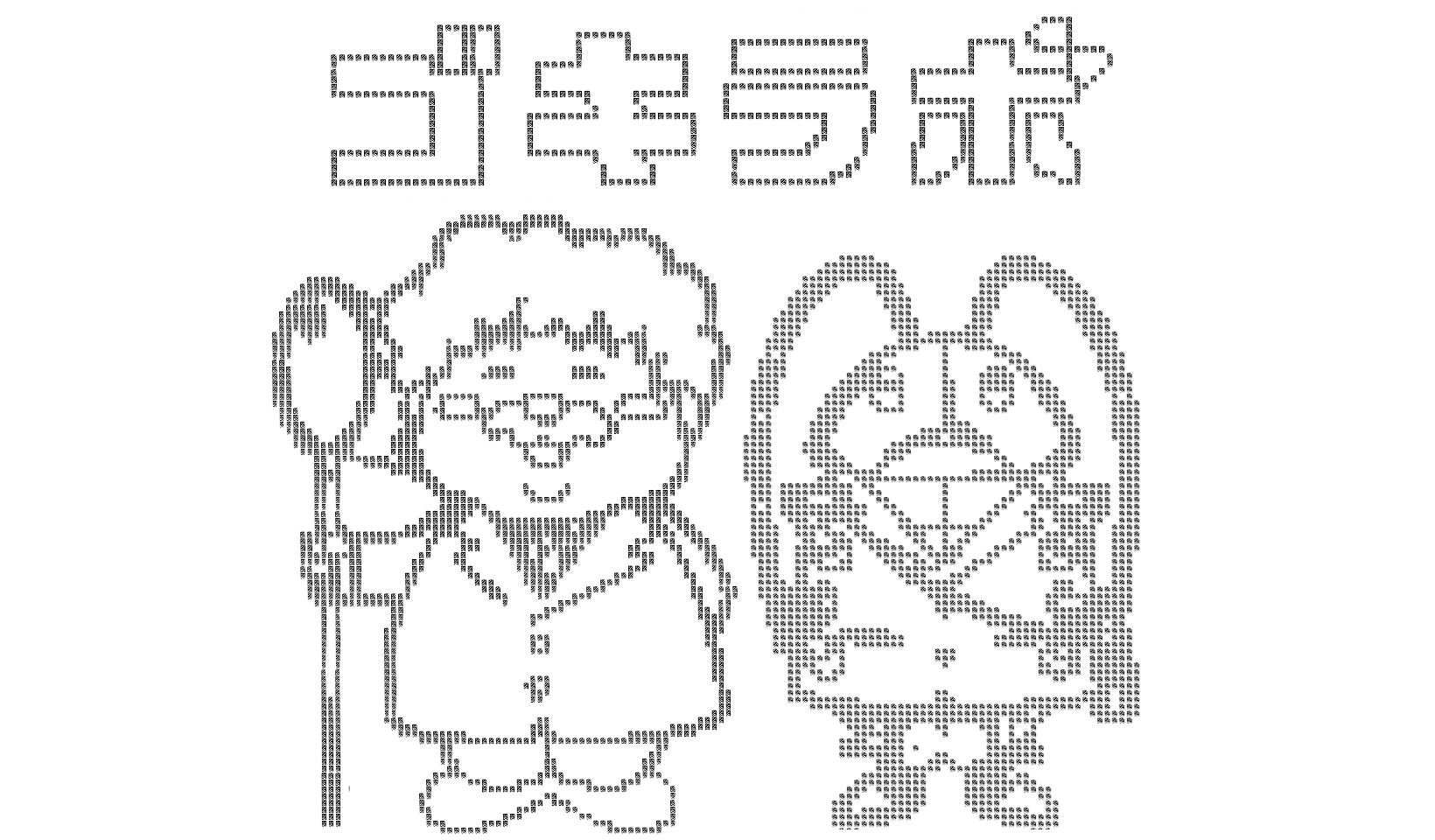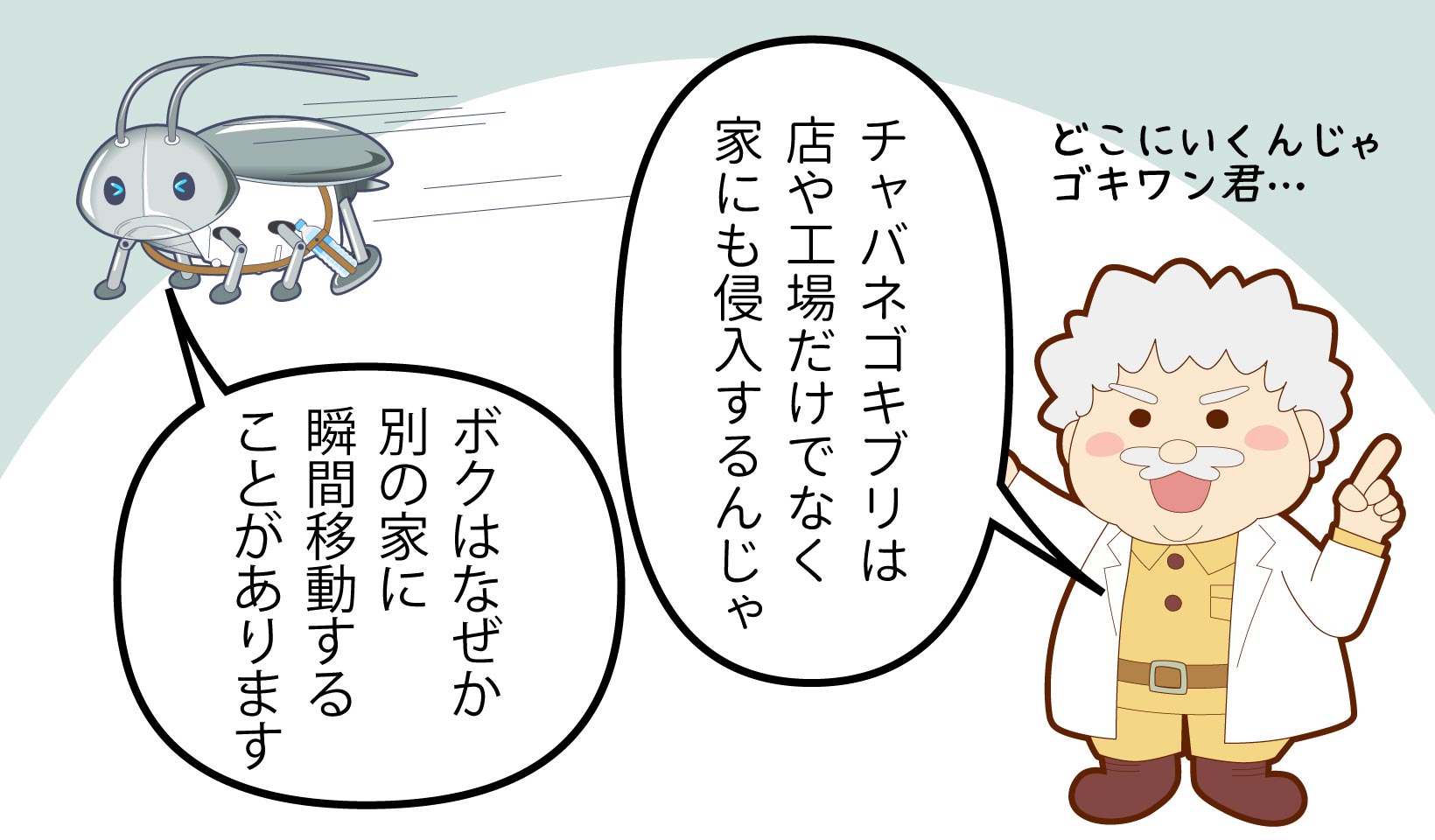最近では、「G」などと呼ばれることもあるゴキブリ。名前を呼ぶことすら嫌! ということなのじゃろうが、実は明治時代までは、ゴキブリではなく「ゴキカブリ(御器噛)」と呼ばれておったんじゃ。今回は、名前の変遷からゴキブリの歴史を紐解いていこう!

ゴキブリとの同居は縄文時代から!
ゴキブリと名付けられるはるか昔、いまから約4300年前の縄文時代から私たちとゴキブリの同居は始まっていました。

宮崎市田野町本野原遺跡では、2016年に、縄文時代である約4300年前と約4000年前の土器から、クロゴキブリの卵鞘(らんしょう)の痕跡が発見されています。この発見は、日本においてはじめて、居住空間の遺跡から出たゴキブリの足跡というわけです。
上記で発見されたのはクロゴキブリですが、人間の住みかに侵入するゴキブリの中で、日本在来種とされているのはヤマトゴキブリのみ。外から来た可能性の高いクロゴキブリが、すでに暮らしの中に入り込んでいたということは、日本在来種とされるヤマトゴキブリは、もっと古い時代から私たちと同居生活を開始していたと考えてよいことになりますね。
残念ながら当時の呼び名は不明ですし、呼び名があったのかどうかもわかりません。しかし、ゴキブリの存在自体は、当時の人々にも認識されていたのではないでしょうか。
ゴキブリの誕生や歴史について詳しくは⇒
『最新研究が解き明かす!ゴキブリの起源は3億年前ではなかった!?』
『ゴキブリの歴史・いつ誕生したの?古代のゴキブリからどう進化した?』
「ゴキカブリ」が「ゴキブリ」になった!?名前の変遷
実は、私たちが慣れ親しんでいる「ゴキブリ」という名前が広く定着したのは、長い歴史から見ると比較的最近のこと。残された書物には、ゴキブリ以外の呼び名がいくつか記録されています。
平安時代「(阿久多牟之)アクタムシ」「都乃牟之(ツノムシ)」
ゴキブリの存在が書物に初めて登場したのは、平安時代。
当時の漢和辞典ともいえる『本草和名』(918年・深根輔仁著)には、「阿久多牟之(アクタムシ)」、「都乃牟之(ツノムシ)」という名が記されています。もう少し後の書物『伊呂波字類抄』(平安時代末期・橘忠謙著)では、「アキムシ」という名称も記されています。これらは、日本在来種で人家に侵入するヤマトゴキブリだと考えられています。
「阿久多牟之」はゴミをあさる虫、「都乃牟之」は触角のある虫という意味じゃ。ゴミをあさる虫という名がそのまま付けられているということは、当時の人々もあまりいい印象を抱いていなかったことが想像できるのお。

江戸時代「油虫(アブラムシ)」「御器噛(ゴキカブリ)」
江戸時代になると、「アブラムシ」という名称が当時の百科事典に登場します(『訓蒙図彙(きんもうずい)』(1666年))。同じく百科事典の『和漢三才図会』(1713年)には、「油虫(アブラムシ)」と「御器噛(ゴキカブリ)」という名が記されています。

『和漢三才図会』の説明文からは、油虫はチャバネゴキブリ、御器噛はヤマトゴキブリかクロゴキブリであることが推測できます。油虫は、油ぎったように見える体に由来し、御器噛は、ふたつきのお椀(御器)をかじる虫というところからその名が付けられました。
さらに、『和漢三才図会』では、「蜚蠊(フイレン)」という漢字があてられ、あぶらむしが併記されているページがあります。蜚蠊は、中国で使用されていたゴキブリの名称です。

『和漢三才図会』 出典/国立国会図書館ウェブサイト
※クリックで拡大
当時は、ほかにも地域によってさまざまな呼び名がありました。
『本草網目啓蒙』(1803-06年)には、ツノムシ・アブラムシ・ゴキカブリ・ゴキクラヒムシ・ゴキカブラウ・ゴゼムシ・アマメ・ヘイハチアマメ・ママクヒムシ・ゴキアラヒムシなどの名が収録されています。このうち、「アマメ」は、海岸に生息するフナ虫の方言で、走る姿が似ていることからそのまま方言として広がったのではないか、といわれています。
「ゴキカブリ」を誤記してゴキブリに!
「ゴキカブリ」でも「アブラムシ」でもない、「ゴキブリ」は、明治に入ってやっと登場します。
「ゴキブリ」の語源は「ゴキカブリ」だといわれていますが、ゴキカブリがつまる場合は、促音便で「ゴッカブリ」になります。『虫の博物誌』(小西正泰博士著)によると、実際に、関西や九州北部では、「ゴッカブリ」あるいはその変形の「ボッカブリ」と呼ぶところがあるとのことです。
では一体なぜ、「ゴキブリ」になったのでしょうか?
昆虫学者の小西正泰博士は、「だれかが、「ゴキカブリ」を「ゴキブリ」と誤記したものに違いない」と推測しています。
その理由として、当時は「ゴキカブリ」の名がある程度広まっており、「蜚蠊」という漢字には「ゴキカブリ」とルビが振られるはずが、誤って「ゴキブリ」と記されたことから、そのまま一般化して今日に至ったわけではないかと『虫の博物誌』で説明されています。
「コガネムシは金持ちだ~」はゴキブリ歓迎ソング♪
ゴキブリの異名の中には「黄金虫(コガネムシ)」もあることはご存知でしょうか?
黄金虫は金持ちだ
金蔵建てた 蔵建てた
飴屋で水飴 買って来た
と歌われる童謡『黄金虫』。
元日本昆虫学会会長の石原保博士の説によると、この黄金虫は、チャバネゴキブリだというのです。
『黄金虫』を作詞作曲した野口雨情の生まれ故郷である茨城県では、ゴキブリのことを方言でコガネムシと呼んでいました。さらには、チャバネゴキブリが屋内に増えると財産家になるといわれてもいました。つまり『黄金虫』は、ゴキブリを歓迎する歌だといえますね。
たしかにチャバネゴキブリの色は黄金色をしておるし、卵の形も小判に似ておる。さらにメスは、がま口財布のような形をした卵鞘を持ち歩くから、そのような言い伝えがあっても不思議ではないのお。
ゴキブリの卵の特徴について詳しくは⇒『【画像付】ゴキブリの卵の特徴・産卵時期に場所、見つけた時の駆除方法』

ちなみに、外国にもゴキブリソングがあります。
メキシコの民謡『ラ・クカラチャ』。
スペイン語でクカラチャ(cucaracha)は、ゴキブリを意味するので、タイトルは「ザ・ゴキブリ」。この歌は、1910年から始まったメキシコ革命において、民衆たちが生み出した歌だといわれています。『ゴキブリ大全』(デヴィット・ジョージ・ゴードン)によると、敵の将軍のことを揶揄した歌詞を含め、さまざまな替え歌が生まれ歌われたとのことです。
さらに『ラ・クカラチャ』は、有名ミュージシャンによってカバーされ、歌い継がれてもきました。『車に揺られて(ラ・クカラチャ)』という邦訳の作品もあります。
駆除剤の広がりとともに「ゴキブリ」の名が定着!?
はるか昔から、人間の住みかに侵入してきたゴキブリ。これまでの呼び名や記録を見る限りでは、『黄金虫』のような例外はあるものの、昔から嫌われ者だったといえます。つまり、駆除の対象であることは昔も今も大差ないということです。
ここからは、ゴキブリ対策の歴史を簡単に見ていきましょう。
昔はどんなふうに駆除していた?
『虫の博物誌』には、江戸時代中期のゴキブリ対策が紹介されています。
- 油紙製のカラカサを用いた捕獲器
- カワラニンジンを使ったゴキブリよけ
カラカサは油紙にゴキブリが集まるのを利用した方法で、カワラニンジンについては忌避効果があったと考えられます。
明治時代には、ある罠が有効だと昆虫学者の佐々木忠治郎博士によって書き記されています(『昆虫学』2巻5号・1907)。
それは、漬物を漬ける円筒の陶器の底にゴキブリが食べそうなものを入れ、筒の内側上部に種油を塗って、ゴキブリを逃げられなくするという捕獲方法です。その後、陶器がガラスとなり、油がバターとなって、バタートラップ法として一般に広まりました。


これらの対策例を見る限りでは、そこまで忌み嫌われているイメージは沸いてきませんね。案外と嫌われていなかったりして……なんて希望を持ってしまいそうです。
ゴキブリ駆除の本格化は戦後以降
ゴキブリが、人間に悪影響をもたらす衛生害虫として広く認識され始めたのは、戦後以降の話です。
戦前から戦後にかけて(1940~1950年代)、海外では強力な有機塩素系殺虫剤(DDT、BHCなど)が開発されました。こうした薬剤は、それまで日本では対応できずに困っていたシラミやノミの駆除に使用され、多くの人がシラミやノミに悩まされることがなくなりました。ところが、すでに1950年代には、これらの有効成分に対してシラミの抵抗性の発達が多くの国でみられるようになり、その後、環境における残留も問題となりました。
一方で、ゴキブリに対する強力な駆除剤も販売されるようになりました。有機塩素系殺虫剤はゴキブリにも有効でしたが、とくに温暖なコンクリートビル、工場施設、飲食店などに定着し、急速に世代を繰り返すチャバネゴキブリでは、シラミ同様に抵抗性の発達が早かったのです。
抵抗性ゴキブリについて詳しくは⇒『驚異の生命力!スーパーゴキブリ(抵抗性ゴキブリ)は殺虫剤が効かない!』
その結果、1961年に販売された”バルサンジェット”タイプを皮切りに、それまで農薬として使用されてきたカーバメイト剤、有機リン剤、ピレスロイド剤などを使用したスプレー式の駆除剤やくん煙剤も販売され、その後も実に様々なタイプ駆除剤が開発されています。
殺虫剤の有効成分について詳しくは⇒『🔰殺虫剤有効成分の効果と特長(ピレスロイド系、有機リン系、忌避剤など)』

1973年に登場した捕獲器“ごきぶりホイホイ”は、当時大流行しました
明治に登場した「ゴキブリ」という名は、駆除剤の広がりとともに、ゴキカブリという元の名を消し去る勢いで根付いていったともいえますね。
そしていまや、ゴキブリは「G」と隠語で呼ばれることもあるくらいに、その名を口にするのもはばかられるほどの不快害虫として君臨しています。
現在販売されているゴキブリ駆除剤について詳しくは⇒
『ゴキブリを見ずに駆除!ベイト剤・捕獲器・くん煙剤・忌避剤の比較』
『ゴキブリ退治・スプレー式駆除剤(殺虫剤/凍結/泡)の成分・効果・安全性』
まとめ
ゴキブリは、いまや誰もが知る害虫の名前ですが、もともとは以下のように、別の名で呼ばれていました。
| 平安時代 | 江戸時代 | 明治時代以降 |
|---|---|---|
| 阿久多牟之(アクタムシ) 都乃牟之(ツノムシ) |
油虫(アブラムシ) 御器噛(ゴキカブリ) (ゴキクライムシ・ゴキカブラウなどの方言多数あり) |
御器噛(ゴキカブリ) ゴキブリ |
明治時代になってやっと「ゴキブリ」が登場するわけですが、それはなんと、ゴキカブリをゴキブリと誤記したのが始まりだといわれています。
誤記によってゴキブリになるなんて意外な由来ですよね。
そしてその名は、駆除剤の広がりとともに誰もが知る不快害虫として定着することとなったのです。
- 『虫の博物誌』(朝日新聞社)
- 『ゴキブリ3億年のひみつ』(講談社)
- 『ゴキブリの話』(北隆館)
- 『ゴキブリ大全』(青土社)
- 『衛生害虫ゴキブリの研究』(北隆館)
- 熊本大学「縄文時代のゴキブリの卵を発見!」プレスリリース
- 朝日新聞 2008年2月17日配信記事
- 『和漢三才図会』国立国会図書館ウェブサイト
- 『本草和名』918,深根輔仁
- 『伊呂波字類抄』平安時代末期,橘忠謙
- 『本草網目啓蒙』1803-06
- 『昆虫学』2巻5号,1907,佐々木忠治郎