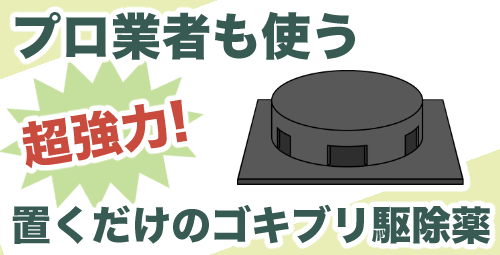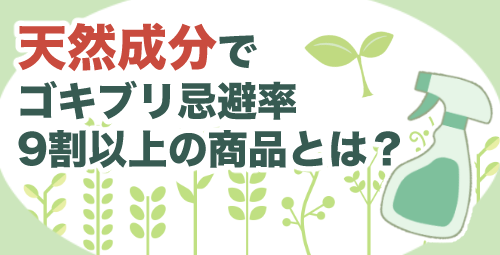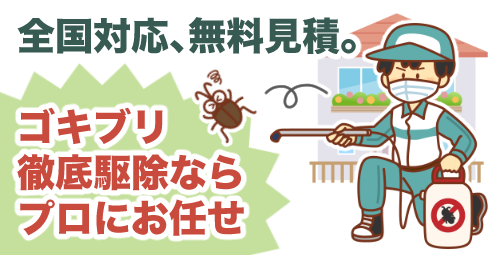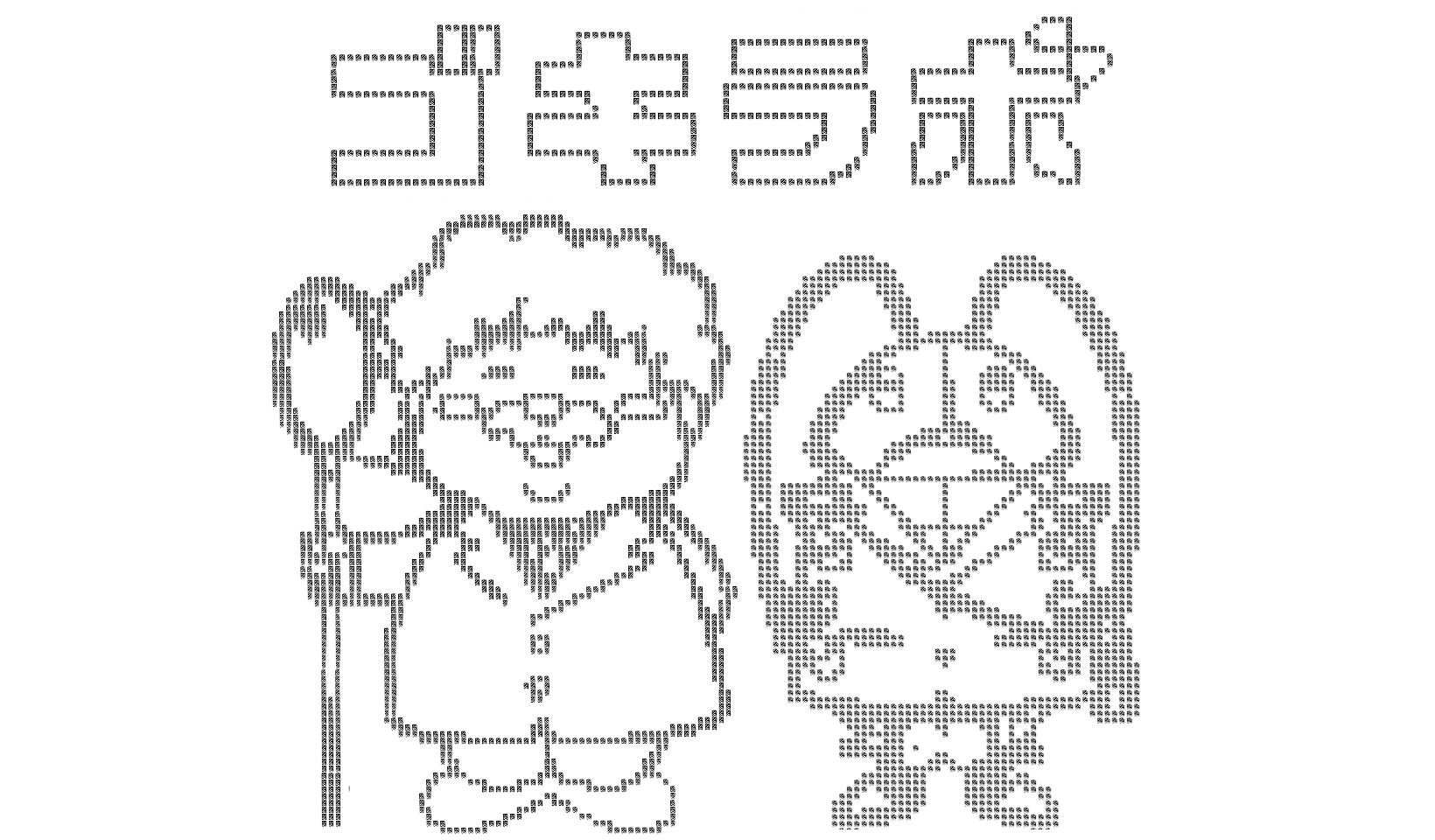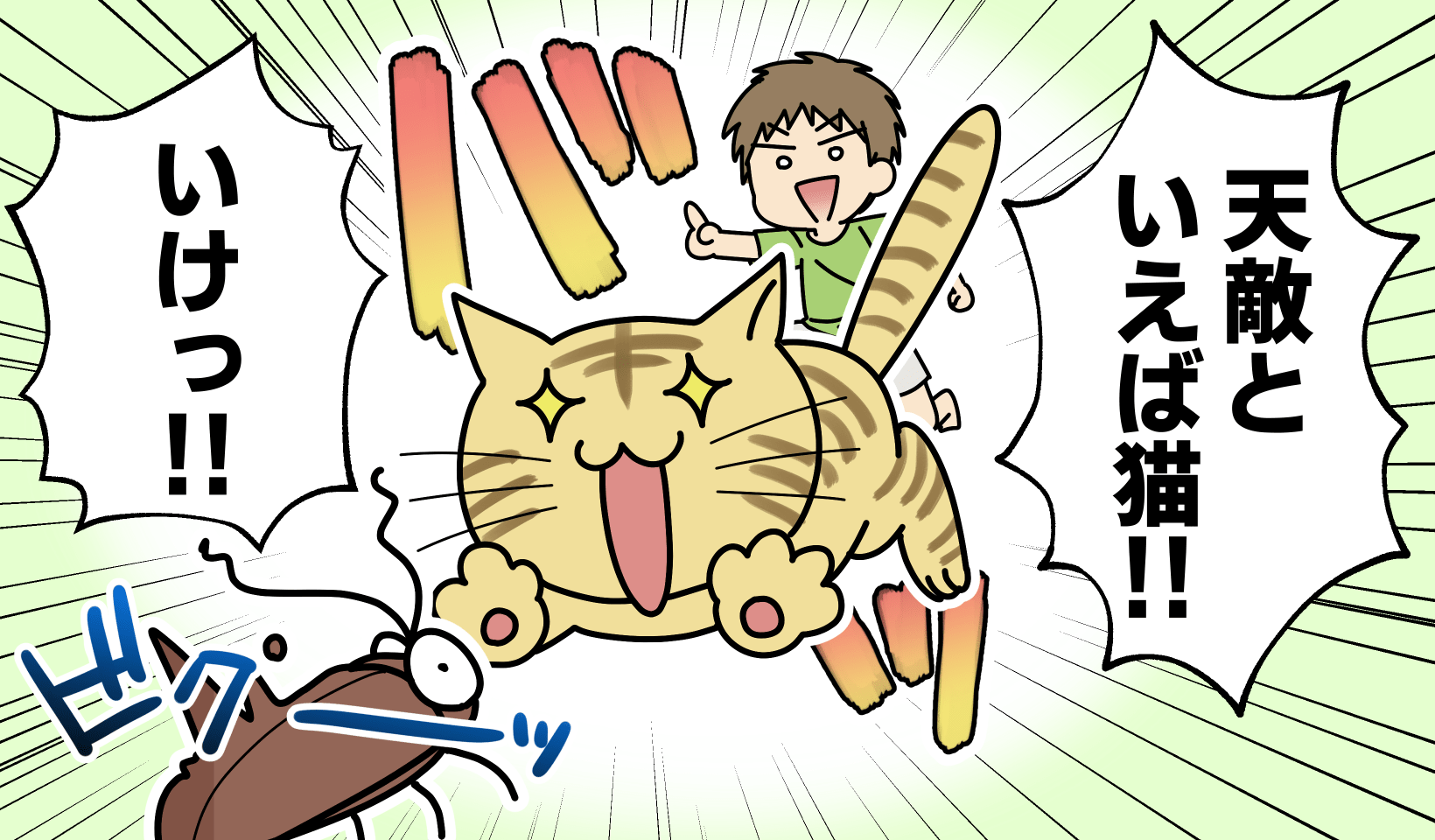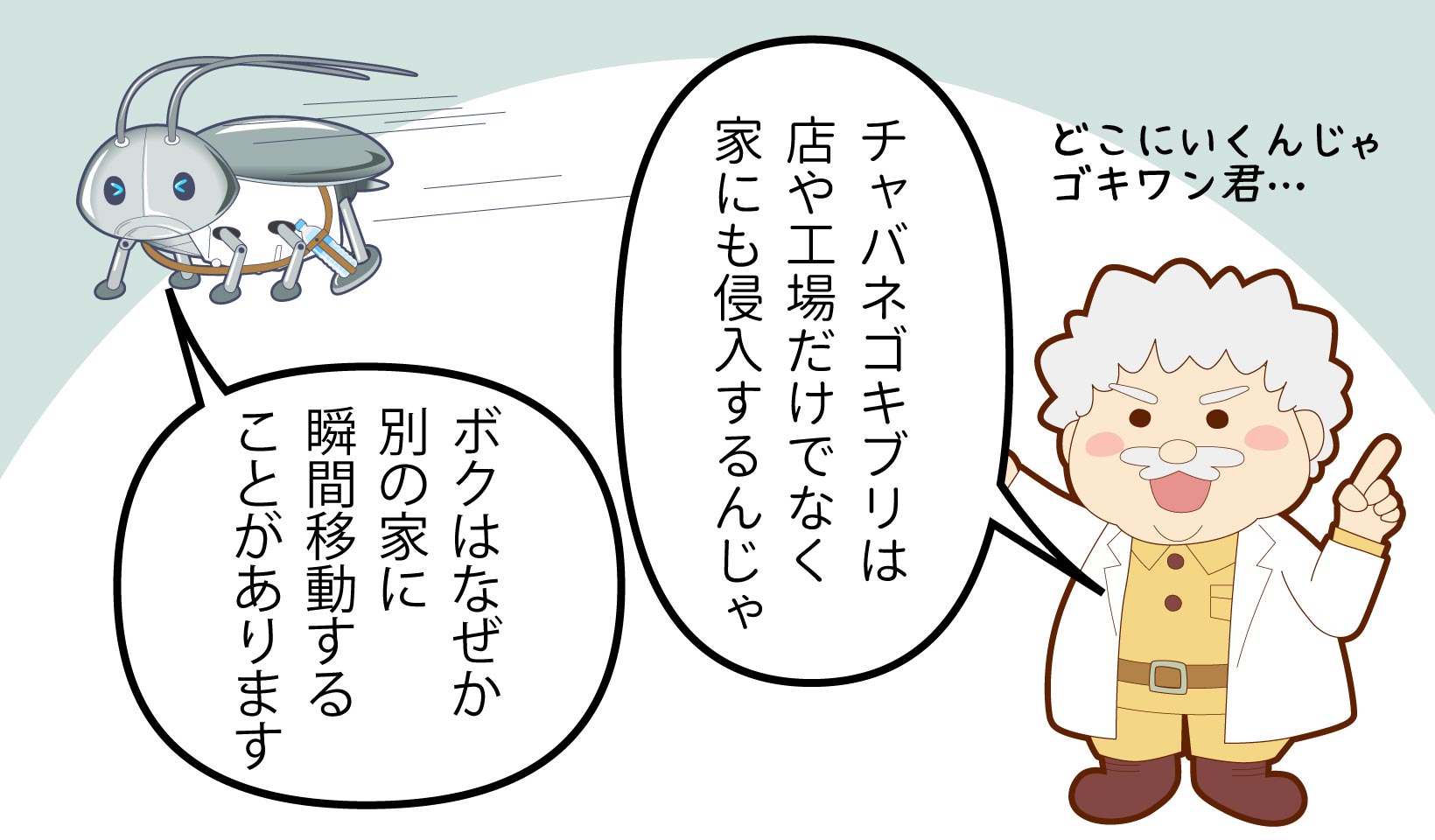ゴキブリはいつから地球におるか、みなさんはご存じじゃろうか? 実は、われわれ人類よりもはるか昔から生き続けておるんじゃ。なんと、遡ること3億年以上も前に、ゴキブリは誕生したんじゃ。では、その当時のゴキブリはどんな姿形をしていたのか? そして、人類との同居はいつから始まったのじゃろうか? さっそく見ていこう。

まさに「生きた化石」!ゴキブリは3億年前から生きてきた
ゴキブリの誕生は、3億年以上前の古生代石炭紀。一方、人類の祖先である「猿人」が誕生したのは約200万年前。こう比べてみると、ゴキブリは、私たち人間なんて比べ物にならないほど古くから地球に存在している、「大先輩」であることがよくわかります。
では、3億年以上前の古生代石炭紀というのは一体どんな時代なのでしょうか?

『ゴキブリ3億年のひみつ』(講談社)から作成
石炭紀とは、海で誕生し、海で進化を遂げた生き物たちが陸への上陸を果たした後の、両生類や昆虫たちが繁栄した時代。高温多湿で、シダ植物が繁茂し、地球上にはじめて森林ができた時代でもあります。そのような環境下で、ゴキブリは、森林の植物や小さな昆虫の死骸を糧に大いに繁栄しました。その証拠に、数百種ものゴキブリの化石が発見されているのです。
石炭紀にはさまざまな種類の昆虫が出現しましたが、その多くは絶滅し、現代まで子孫を残しているのは、ゴキブリとカゲロウ、バッタなどの直翅類の祖先だけです。したがってゴキブリは、現存する昆虫の中ではもっとも長い歴史を持っているといえます。まさに「生きた化石」ですね。
ゴキブリの生態をしっかり把握したい方は⇒『ゴキブリを知る!クロゴキブリ(成虫)の体の構造・寿命・活動時間・隠れ場所』
『ゴキブリ3億年のひみつ』(昆虫学者・安富和男博士著)によると、日本最古の昆虫化石は、山口県美祢市大峰炭鉱付近で発見された、中生代3畳紀(2億3000万年前)の地層で見つかったゴキブリの前翅とのことじゃ。古生代のものは見つかっていないの? といいたくなるとことじゃが、古生代にはまだ日本列島はなかったんじゃよ。

古代のゴキブリと現代のゴキブリの違いとは?
古生代石炭紀生まれのゴキブリは、いま生きているゴキブリとそう大きくは変わりません。化石を見れば、ゴキブリだと私たちが認識できる形態的な特徴を、当時からすでに備えていたということです。体長も、2cm~8cmくらいと、現代のゴキブリと大差ありません。
ただし、以下の2つの違いがあります。
- 1)翅
- 2)産卵管
1)と 2)をそれぞれ見ていきましょう。
1)翅

『ゴキブリの話』(北隆館)から作成
化石に刻まれている前翅(背面を覆う翅)は、現代のゴキブリよりも大きく長い形態でした。おそらく、飛翔の際に役割を果たす、または、腹部の保護などに役立っていたと考えられます。
では、なぜ前翅は小さく進化したのでしょうか。
昆虫学者の石井象二郎博士は、その理由を、「穴に潜む生活に適応していったことと関係がある」と分析しています。地球の環境が変わり、ゴキブリは生き抜くために地表下で暮らすようになりました。その変化に対応するように、彼らの翅や目は退化し、扁平で脚の発達した体に進化したのではないかと、考えられるそうです。(『ゴキブリの話』(北隆館))
また、翅脈にも違いが見られるという指摘もあります。ただし、その変化がどのような意味を持つのかは不明です。
現代のゴキブリの体については⇒『ゴキブリを知る!クロゴキブリ(成虫)の体の構造・寿命・活動時間・隠れ場所』
2)産卵管

『ゴキブリの話』(北隆館)から作成
産卵管とは、その名の通り、卵を地中などに産みつけるための管です。古生代の化石の中には、この産卵管を持ったゴキブリが存在しています。現代のゴキブリには、産卵管は見られません。
産卵管を持ったゴキブリは、中生代まで続いたことは明らかになっていますが、なぜなくなってしまったのかはわかっていません。わかっているのは、産卵管を持ったゴキブリは消え、産卵管を持たずに、卵を丈夫な鞘(卵鞘)で包んだゴキブリが生き残っていまに続いているということ。後者のほうが生き残ったのは、より繁殖する確率が高かったということなのかもしれませんね。
現代のゴキブリの卵については⇒『【写真】ゴキブリの卵の特徴を解説!死ぬときに卵を生む?どこに産卵する?』
最新研究では「ゴキブリの起源は約2.6億年前」
実は、「ゴキブリの起源は3億年前ではなく約2.6億年前だった」という研究結果が筑波大学より発表されています(2019年2月1日プレスリリース)。
この研究結果は、これまで解説してきた定説「ゴキブリの起源は3憶年前」を覆すものです。しかも、単なる時代のズレではなく、ゴキブリ目とカマキリ目との分岐がいつ起きたのか、という進化の変遷を解明したのだと研究チームは発表しています。
研究について詳しくは⇒『最新研究が解き明かす!ゴキブリの起源は3億年前ではなかった!?』
今後の研究によっては、「ゴキブリの起源は2.6億年前」が定説となるかもしれませんね。
いつから始まった?ゴキブリと人類の同居

ゴキブリは、そもそもは森林で暮らす昆虫です。もちろん、現代においてもその大半は森林に生息しており、人間の生活域に入り込んでいる種類はごくごくわずかな種類に限られています。
ではその“わずか”なゴキブリたちは、いつ頃から人間と同居するようになったのでしょうか?
安富和男博士は、人類が火を使いはじめた頃からではないか、と著書である『ゴキブリ3億年のひみつ』で語っています。つまり、火を使って暖をとり、煮炊きをする生活は、ゴキブリにとって、暖かな隠れ場所と餌の供給源となったというわけです。
また、石井象二郎博士は、人類が穴ぐらのような住居に住み、食糧を蓄えるようになってからではないか、と著書である『ゴキブリの話』に書き記しています。
いずれにしても、人間からすれば、ずいぶんと長い間共存してきたんだなあ、と感慨深くなりますが、ゴキブリからすれば、比較的新しくまだまだ歴史の浅い同居生活といったところでしょう。
日本人とゴキブリの同居はいつから始まったのか、というと、縄文時代にはすでにスタートしていたことがわかっています。
2016年に、宮崎市田野町本野原遺跡で、縄文時代である約4300年前と約4000年前の土器から、クロゴキブリの卵鞘(らんしょう)の痕跡が発見されたのです。この発見は、日本においてはじめて、居住空間の遺跡から出たゴキブリの足跡です。
屋内ゴキブリの分布を広げたのは人間!?
人間と同居するゴキブリは、交易の発達にともない、その分布を世界各地へと広げていったのだと考えられます。彼らを一気に遠方の地域へと運んだのは、船、鉄道、飛行機の存在でした。

例えば、チャバネゴキブリは、アフリカ北部から東ヨーロッパを経て広まったとされています(Cornwell,1968)。最初は、アフリカからギリシャなどの船で東ヨーロッパに運ばれ、ビザンチンや黒海沿岸地帯等に広がり、その後徐々にヨーロッパに分布を拡大していったと考えられています。また、イギリスには、クリミア戦争に出征した兵士の荷物にくっついて侵入したと言われています。
ちなみに、日本の一般家庭でよく見られるクロゴキブリは、北アメリカ南部、南米、台湾、香港、南中国などにも分布していますが、原産地や移動経路は明らかになっていません。
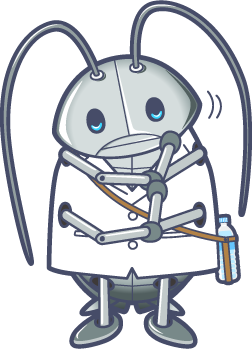
自力では長距離移動しないゴキブリたちを世界各地へと広めたのは、人間だというわけですね……。もちろん、ゴキブリが勝手にくっついてきてしまったわけですが。3億年以上生き続けてきた昆虫は、自分たちが生き残る術をよく知っているのかもしれません。やっぱり侮れません、ゴキブリ。
まとめ
今回は、原始のゴキブリの姿や人類との同居の始まりなど、ゴキブリの歴史について見てきました。
ゴキブリが3億年以上生き続けてこられたのは、その繁殖力や何でも食べる雑食性、そして、形態的、生理的な利点といったさまざまな理由が組み合わさった結果だと考えられます。さらに、現代のゴキブリ(チャバネゴキブリ)は、人間が振りまく殺虫剤への抵抗性も発達させているのです。
抵抗性について詳しくは⇒『驚異の生命力!スーパーゴキブリ(抵抗性ゴキブリ)は殺虫剤が効かない!』
繁殖力について詳しくは⇒『1匹いたら100匹いる?ゴキブリのやばい繁殖力!まさかの単為生殖も』
あらためて、すごい生き物だなと尊敬の念すら抱きたくなりますよね。とはいえ屋内に侵入してくるゴキブリと仲良くできるかというと、そううまくはいきませんね。やはり、嫌なものは嫌! という人が大半のはずです。
相手は、3億年の歴史を持つ昆虫ですから、こちらも心して対策しましょう。大丈夫、あなたにはゴキラボがついています!
もっとも効果的な対策を知りたい方は⇒『隠れゴキブリ一網打尽!ベイト剤(毒餌)の効果的な設置場所・時期・個数を徹底解説』